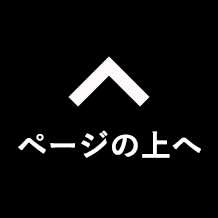いしみがわのかんじょうかけ
石見川の神縄懸
大阪 / 河内長野市 ( かわちながのし ) 関連分類: 祭り
毎年1月3日、石見川地区の集会所で行われる。神縄懸の中心となるのは年行事(ねんぎょうじ)と呼ばれる役割であり、地区内の住民から2名が担当する。かつてはこの日に、村の行事担当者である年行事が交代する行事である「年行事ワタシ」が行われていた。
行事の当日、集会所に年行事や地区の役員が集合し、「蛇(じゃ)」と呼ばれる勧請縄を作り始める。河内長野市内では勧請縄かけが3例確認されているが、それぞれに行事の名称や勧請縄の形態などに個性が見られる。石見川の場合は、勧請縄とともにヒノキの枝で杖を作る点が特徴である。長さ約1mのヒノキの枝を削り、干支の守り本尊の梵字と、「五穀豊穣 地区内安全」という祈願文を記した杖を作る。
完成した約3mの勧請縄を年行事が背負い、地区の境目まで走っていく。ヒノキの杖は、設置された勧請縄の横に立てる。勧請縄は一年間吊るしたままにしておき、翌年の神縄懸の際に外す。河内長野市における勧請縄の多様性がうかがえる行事の一つである。
市区町村または関連団体へのリンク
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/
※お祭り・行事などの最新の開催状況は、各地域の情報をご確認ください